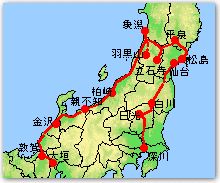深川の芭蕉と旅立ち [地図]
|
「おくのほそ道」より 「おくのほそ道」全編 月日は百代(はくたい)の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。舟の上に生涯をうかべ馬の口とらへて老を迎ふる者は、日々旅にして旅を栖(すみか)とす。古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊(ひょうはく)の思ひやまず、海浜にさすらへ、去年(こぞ)の秋江上(こうじょう)の破屋(はおく)に蜘蛛(くも)の古巣を払ひて、やや年も暮、春立てる霞の空に、白川の関越えんと、そぞろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神(だうそじん)のまねきにあひて取る物手につかず、股引(もゝひき)の破(やぶ)れをつづり笠の緒(お)付けかへて、三里に灸(きゅう)すうるより、松島の月まづ心にかゝりて、住める方は人に譲り、杉風(さんぷう)が別墅(べつしよ)に移るに、 |
芭蕉庵があったとされる芭蕉稲荷。芭蕉が日本橋からここ深川に移り住んできたときには、まだ開拓途中で湿地や荒れ地の多いところだったようだ。芭蕉門人の杉山杉風(さんぷう)の番小屋だともいわれている。
芭蕉稲荷になぜ蛙の置きものなのか。芭蕉は本当にこの石の蛙を愛玩していたのだろうか。どうも「かわず飛び込む水の音」の縁だけのように思われるのだが。
そんなことはどうでもよいのだが、それにしても「おくのほそ道」の最初の文章は暗記するほど繰り返し読んだが、わかったようでよくわからない。過ぎゆく時間や人生を旅と感ずる感性は芭蕉特有のものか。旅への、漂泊へのあこがれは何処から来たりて何処かへ去っていく、流れていくもの、諸行無常の情感へのあこがれか。
「旅に病み夢は枯野をかけめぐる」、こんな句を残した芭蕉が気になりはじめたのはいつの頃からだろう。自分でもよくわからないのだが、この句のイメージが気になって仕方がない気分になるのは、やはり仕事に疲れ、年をとったせいなのだろうか。そんな句を作った芭蕉という人の生き方が気になった。芭蕉をもっとよく知るためには、芭蕉を求めて旅をしてみるのが一番とおもい立って、「おくのほそ道」を携えて旅に出た。
まず、深川にあった芭蕉庵を訪ねることから始めた。写真は、芭蕉稲荷。この場所で、芭蕉が気に入っていたという石造りの蛙が発見されたことから、芭蕉庵のあった場所とされている。石の蛙は大正6年の大津波の時、水が引いたあとから発見されたという。芭蕉稲荷の狭い庭には石蛙がいっぱい置いてあった。発見された蛙は、芭蕉稲荷の近くにある芭蕉記念館で展示されている。
この蛙は残念ながら撮影禁止。
この頃の深川隠棲の時代といわれる芭蕉については、「深川の芭蕉」を参照。
芭蕉稲荷にある「芭蕉庵跡」 の石碑。バックの青竹のカラーがはげている。悲しい。石の蛙だけで芭蕉庵跡とするのはいかがなものか、という気がしないでもないが、まっ、この辺りだったのだろうということか。
旅への路銀のたしにか、杉風(さんぷう)からもらったか借りていた芭蕉庵を、人に売って(譲って)出てしまう。芭蕉が侘び住まいしていたその草庵には雛が飾ってある。小さな娘のいる家族が入ってきた、この草庵もなにがしか華やいでいくのだろうか。こうして人の世も移り変わっていく。
芭蕉稲荷の中に「芭蕉庵跡」の石碑がある。バックのプラスチックの囲いの緑の塗装がはげていて、芭蕉の風流はない。芭蕉稲荷の周りには、「芭蕉稲荷大明神」ののぼりがあげてあるが、なぜ「芭蕉稲荷大明神」なのか、少し悲しいものを感じるが滑稽でもある。野ざらしの生き方を本望とした芭蕉だから、稲荷大明神でも甘受してくれるだろうか。
「高く心を悟りて、俗に帰る」をよしとした芭蕉の生き方にとって、「俳聖」 でも稲荷大明神でも笑ってくれるだろう。
芭蕉庵の跡は深川沿いにあるが、芭蕉の墓所は遺言により大津市の義仲寺(ぎちゅうじ)にある。
「芭蕉庵跡」の近くの墨田川の川べりに芭蕉記念館が管理する小さな公園がある。この下の写真の粋な門をくぐり階段を上がると、公園がある。公園には、芭蕉の銅像が北を向いて座っている。
草の戸(と)も住みかはる代(よ)ぞ雛(ひな)の家
住みなれた草庵を出て旅に生きようとする芭蕉は、ささやかな庶民の生活を対比的に句にした。芭蕉は退路を断ち切って、おのれの生きざま、旅のへの決意を表明したのかもしれない。
小名木川が墨田川に合流するそのへりに、芭蕉記念館が管理する小さな公園がある。芭蕉は、隅田川の川べりにただずんで、旅の空へあこがれて、漂白の思いを焦がしていたのだろうか。
「貰うて喰(くら)ひ、乞うて喰ひ、やをら飢(かつ)ゑも死なず、年の暮れければ
目出度き(めでたき)人の数にも入らん老の暮」(あつめ句)
弟子や門人からの喜捨で生計を立てていた芭蕉の生活は、容易なものではなかったが、富豪のパトロンなども少なくなかったようで、それなりの供応も受けていたようだ。
望んでいた生活態度だったはずだが、さすがに「もろうて食らひ、乞うて食らう」ような生活でも、どうやら年も越せそうだ、と自嘲ぎみに句にしている。後半生の老成した芭蕉にはみられない、なんというストレートな表現、何度読んでもゾクゾクするような生々しさ、何故か快感が走ってしまう。
芭蕉は、自分の生活のあり様をほとんど乞食と自覚しているのである。「おくのほそ道」では居直って自分のことを「乞食の翁」と呼んでいる。
そんな芭蕉にとって、旅もまた深川草庵の生活の延長にあった。「行きかふ年も又旅人也」とし、「日々旅にして旅を栖とす」る芭蕉には、芭蕉庵での日々の生活もまた旅のようなものだった。
普通の人には、日々の暮らしとは別に旅があるから旅にあこがれもするが、日常に非日常の旅が入り込み、生活が旅と同義になったとき、人はその旅を、生活をどう生きるのか。
芭蕉の像は日本全国にたくさんあるが、どの顔もそれぞれ個性的で違っている。この芭蕉は立派ではあるが、ちょっとふっくらした穏やかな顔つきをしている。この顔が「おくのほそ道」の旅が始まると、苦行僧の顔つきに変わっていくような気がする。
この時代、東北の旅は死を覚悟しなければならない厳しいものだった。芭蕉はそこに身をさらし、己の生き方と俳諧の別の道を探し求めていたのではないか。
この時期の芭蕉の句
雪の朝ひとり干鮭(からさけ)を噛み得たり
芭蕉野分けして盥(たらい)に雨を聞夜哉
櫓(ろ)の声波をうって腸(はらわた)氷る夜やなみだ
芭蕉の孤独と寂寥がストレートに表現されている。芭蕉37歳、さてどうやって生きていくか。芭蕉の思いは何だったのか。「捨てて、捨てて捨てえぬ思いして」、なお俳諧が残ってしまう。
芭蕉は旅を、ほとんど自分の人生と同義に考えていた。そして芭蕉にとって俳諧こそが人生だった。すべてを捨てて旅に出ようと思った。それは俳諧の道を究めるための旅、風流の誠を追い求める旅となるべきものだった。事実、芭蕉は「おくのほそ道」を、ものすることになった。
公園の芭蕉はこんな感じで鎮座している。周りの様子が現在の都会のたたずまいでもあり、芭蕉にとっては居心地が悪そうな感じがする。像のあたりには芭蕉の名のもとになり芭蕉が愛した芭蕉の葉が植えられている。
芭蕉の門人、森川許六が描いた「芭蕉行脚図」が芭蕉が生きていた頃の作品であるため、実際の芭蕉の旅姿に近いのではないかといわれている。
芭蕉はあごに薄い髭を生やし、鼻がやや大きく、ふっくらとした感じ。黒い道服を着、足にはキャハンをまいて、草鞋(わらじ)をはいている。これが芭蕉の旅装束だったのだろう。
曾良が後ろにいて、いい表情で笑っている。芭蕉の表情がやや暗い。生きて帰れないかもしれない旅への覚悟を固めているといった不安の感じ。

森川許六が描いた「芭蕉行脚図」。芭蕉と曾良(そら)。

芭蕉記念館の庭の石碑。「草の戸も住み代わる世ぞひなの家」
草の戸も住み替る代ぞ雛(ひな)の家
芭蕉記念館の庭の石碑。自然石に掘り込まれた句碑は、芭蕉の句とマッチして味がある。
「野ざらし紀行」が終わった芭蕉は42歳だったが、自分のことを「翁」とよんでいる。人生50年の時代では40歳過ぎれば「翁」となるのだろう。
深川の芭蕉庵での生活は、弟子や支援者からの差し入れでなりたっていて、苦しかったのは事実のようだ。芭蕉庵に集った芭蕉の門人は「深川の八貧」と呼ばれ、その清貧の生活ぶりがうかがわれる。芭蕉は門人や弟子たちから生活に必要な物の提供や奉仕は受けたが金銭は受け取らなかったという。経済活動にはほとんど無頓着だった芭蕉だが、日々の生活と俳諧創出、風雅の道とのぎりぎりのバランスをとろうとする芭蕉の苦心と心意気があった。
芭蕉にとって結んだ庵は仮りのもので、おくのほそ道に旅立つときには、その庵も売り払っている。旅賃の足しにでもしたのだろうか。

芭蕉記念館の庭の石碑。「古る池や蛙飛び込む水の音」 の碑。
そんな「草の戸」にも新しい住人が移り住んできて、お雛さまが飾ってある。小さな女の子がいるのだろう。人も住も変わっていくものだ。
古る池や蛙飛び込む水の音
芭蕉記念館の庭の石碑。
この句は、芭蕉が深川の「芭蕉庵」に住んでいた頃に詠んだもので、芭蕉俳諧の傑作とされる。「おくのほそ道」とは関係ない。
芭蕉は、俳諧の言葉遊びや滑稽から、生活感や自然のありよう、物皆自得(ものみなじとく)の世界を表現しようとする、新しい俳諧を生み出そうと一人苦闘していた。「古池や・・・」は会心の作といわれるが、解釈は難しい。自然にしたがい季節の移り変わりを楽しみながら、質素・閑寂のうちに清貧を愉しむ心、その心がわからないと芭蕉の世界は見えてこない。芭蕉の世界はやはり、いかにもしぶい「わび・さび」の世界である。

江戸時代前期の俳人の句が今なお人々の心をうつのは、芭蕉の句のセンスの新しさと洗練された不易の象徴的な表現のせいだろうか。表現の技巧ではなく、「造化(自然のこと)にしたがい、四時(季節のこと)を友とす」る芭蕉の生き方が普段着の言葉で句となって表出している。自然の、存在するもののもう一つの真実を見出し、表現し得ているからだろう。
芭蕉43歳、同じころの句に次のようなものがある。私の好きな句でもある。
名月や池をめぐりて夜もすがら
酔うて寝ん撫子(なでしこ)咲ける石の上
酒飲めばいとど寝られぬ夜の雪
旅人と我が名よばれん初時雨
芭蕉記念館のすぐ裏手にある隅田川の様子。
ここでは、自分の感情を率直に表現していてわかりやすい。この感性は時代を感じさせず、ういういしくもあり、なにか心安らぐ懐かしいような味がする。これだから、芭蕉はすごい。芭蕉庵の孤独な隠遁生活の厳しい表現が、「古池や・・・」の句作を境に変わってきたといわれている。「野ざらし紀行」や「笈の小文」の旅での作句修行が、芭蕉の俳諧に新しい境地を開き始めてきたのだろう。
芭蕉記念館の裏手にある隅田川。芭蕉はこのあたりの隅田川から見送りの人といっしょに船に乗った。
1689年3月 芭蕉46歳 「そヾろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて取もの手につかず」、「おくのほそ道」の旅に出発。8月に大垣に着くまでの6か月の旅に出た。
弥生も末の七日、明けぼのの空朧々(ろうろう)として、月は有明にて光をさまれるものから、不二(ふじ)の峯幽(かすか)にみえて、上野・谷中の花の梢(こずえ)又いつかはと心細し。睦(むつ)ましきかぎりは宵(よい)よりつどひて、舟にのりて送る。千住といふ所にて舟をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻の巷(ちまた)に離別の涙をそゝぐ。
|